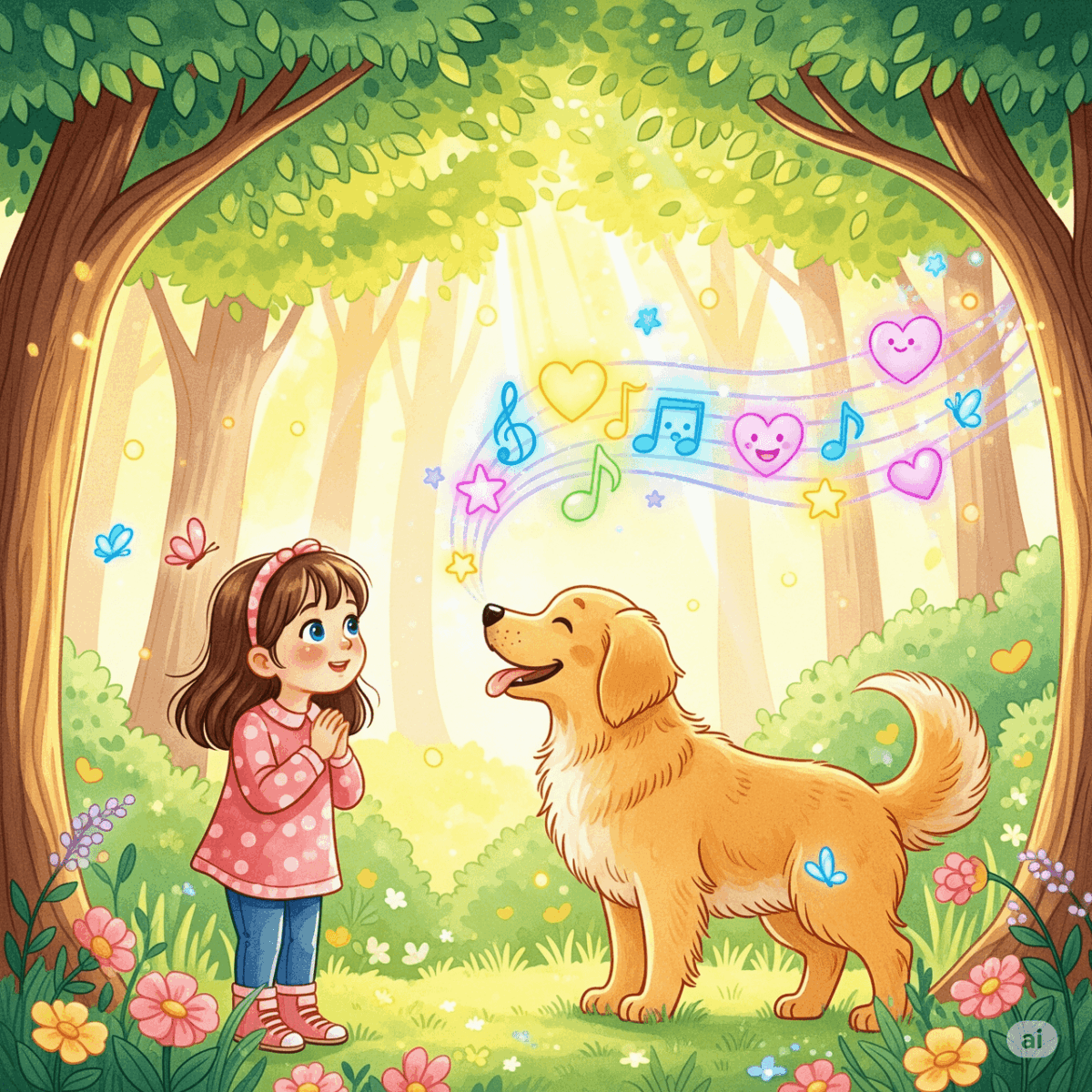アンナ、最近、パパが仕事をしていると突然吠えることがあるね。前はここにいれば静かだったのに、どうしたんだい?
パパ、分かってほしいワン。前は確かにここは安心できる場所だったワン。でも最近、色々なことが気になって仕方がないワン。
色々なこと?例えば?
まず、ハコとフクがドアの前をうろうろするのが嫌ワン。足音がペタペタして、なんだか落ち着かないワン。前は気にならなかったけど、最近は音に敏感になってしまったワン。
なるほど。猫たちの足音が気になるのか。他にも何かある?
外からの音も前より気になるワン。車の音、人の声、鳥の鳴き声…全部が大きく聞こえる気がするワン。パパの部屋は安全だと思ってたけど、外の音は聞こえてしまうワン。
そうか…アンナももう今年の秋には12歳だもんね。年を取ると、人間は音に鈍感になったりするけど、いろいろあるんだな。
そうだワン。前は平気だったことが、今は不安になってしまうワン。でもパパの近くにいたいから、ここにいるワン。ただ、不安になったときは吠えて教えたくなってしまうワン。
アンナの気持ちが分かってきたよ。君なりに一生懸命、不安を伝えようとしてくれてるんだね。
そうワン!パパに「何か嫌なことがあるワン!」って教えたいワン。でも吠えるとパパが困った顔をするから、アンナも困ってしまうワン。
ごめんね、アンナ。君の気持ちを理解しようとしなくて。年を取ると、聞こえ方は変わるけれど、今まで平気だった音に対して不安を感じやすくなることがあるんだ。これは自然なことなんだよ。
パパが分かってくれて嬉しいワン。でも、どうしたら良いワン?吠えないでいる方法はあるワン?
一緒に考えよう。でも獣医さんにも相談した方がいいな。アンナは股関節のトラブルがあって、ときどき痛み止めを飲んでいるよね。痛みがひどくなると、音に対してもいつもより敏感になることがあるんだ。
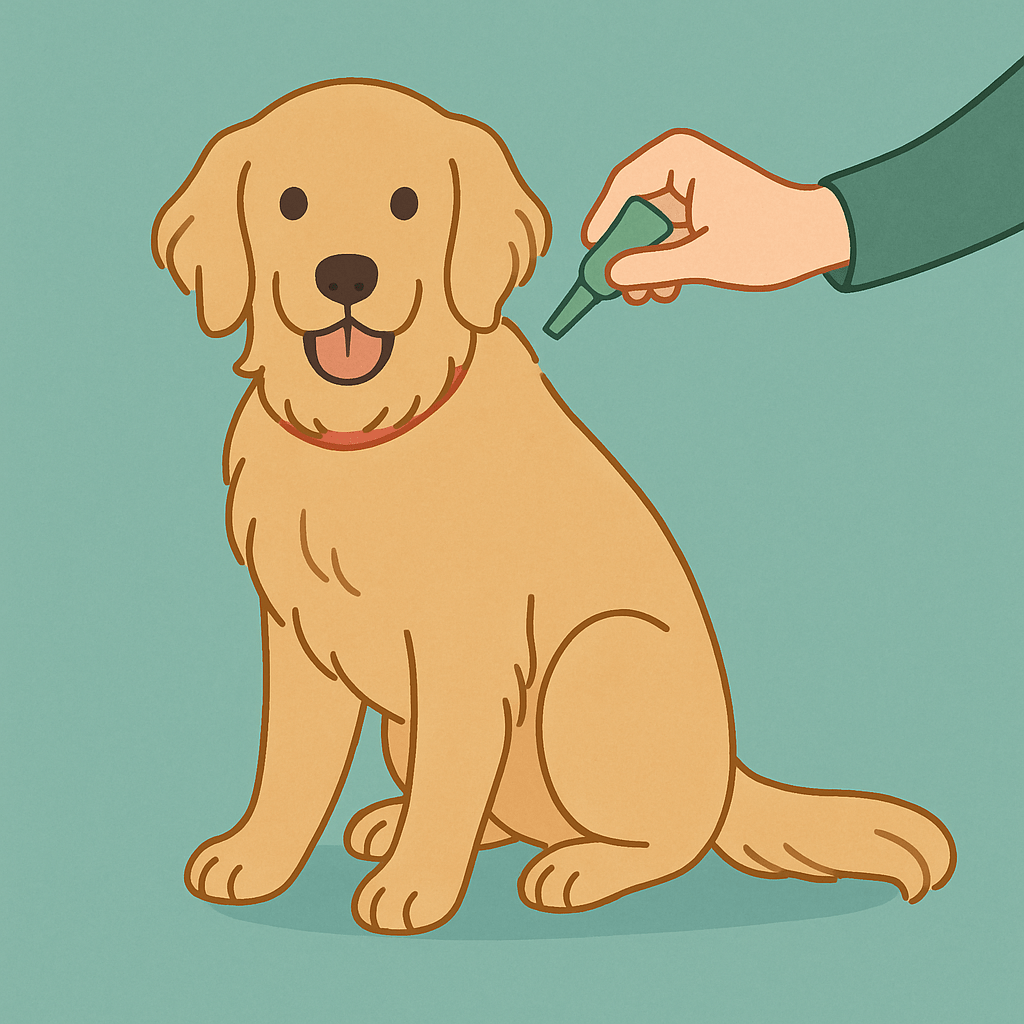
そうなのワン?アンナ、実は最近朝起きるときにちょっと体が重い感じがするワン…それに、後ろ足が痛いときは、なんだかイライラしてしまうワン。
やっぱりそうか。散歩をしていると、股関節の痛みはなさそうに見えてて、安心してたんだ。でも音への反応に影響が出ているかも知れないね。
痛いときは何をされても嫌な気分になるワン。お薬を飲むタイミングの調整は、必要かもしれないワン。
そうだね。それから、猫たちがドアの前に来たときは、パパが「大丈夫だよ」って声をかけてみる。痛みが落ち着いていれば、きっと安心できるよね?
それから、外の音が気になったときも、パパに教えてくれるのは良いけど、小さな声で「ワン」って一回だけにしてもらえる?そうしたら、聞こえたよ、ありがとうって返事をするから。
一回だけワン…難しそうだけど、パパが返事をくれるなら頑張ってみるワン。
そうそう、それからアンナの居場所をもう少し快適にしてみよう。柔らかいクッションを追加したり、パパの匂いがついたタオルを置いたりして、もっと安心できる場所にしよう。
それは嬉しいワン!パパの匂いがあると、もっと安心できるワン。
年を取ることで変化があるのは当然のこと。でも何より大切なのは、アンナが痛みを感じていないか、体に不調がないかを確認することだ。定期的に獣医さんに診てもらって、健康状態をチェックしよう。
健康チェックワン!それは安心ワン。体が元気だと、きっと心も落ち着くワン。
そうだね。体の健康をもっと整えて、アンナの気持ちを理解して、一緒に快適に過ごせる方法を見つけていこう。
パパ、ありがとうワン。アンナの気持ちを分かってくれて本当に嬉しいワン。これからもパパと一緒にいたいワン。
もちろんだよ、アンナ。君はずっと大切な家族だからね。一緒に頑張ろう。
ハコとサンスがこの話を聞いていた
サンス、さっきのアンナとパパの会話を聞いてたニャ?
シニア犬の行動の変化って、どう考えるのニャ?
聞いてたッス!まず先行刺激の変化から見てみるッス。
先行刺激?それって何ニャ?
行動の前に起こる刺激のことッス。アンナ先輩の場合、加齢による認知機能の変化で不安感が増加してるッス。それに聴力低下があると、逆に聞こえる音への注意が集中する現象が起きるッス。
なるほどニャ。確かにアンナはわたしたちの足音を前より気にするようになったニャ。
そうッス!環境刺激への警戒心の増加も先行刺激の変化の一つッス。で、吠える行動の機能を分析すると、「注意を引く」「不安を伝える」という機能があるッス。
行動の機能って、その行動で何を得ようとしてるかってことニャ?
その通りッス!アンナ先輩は吠えることで、パパに「不安だよ」って伝えようとしてるッス。環境への警戒行動としての側面もあるッスね。
じゃあ、どう対応すればいいのニャ?
まず最優先は医学的評価ッス!股関節炎の痛みレベル評価と痛み止めの調整が必要ッス。痛みがあると、全ての刺激に対して過敏になりやすいッスから。
痛みが先なのニャ!てっきり行動を直接変えようとするのかと思ったニャ。
それがよくある間違いッス!痛みを伴う病気が隠れている可能性を常に考慮するッス。関節炎、歯科疾患、内臓疾患など、シニアには多いッスからね。
他の対応策はなんだニャ?
先行刺激の管理として環境調整をするッス。それから代替行動の教示…パパが言ってた「小さく一回吠える」がそれッス。そして強化の提供として、パパからの返事と安心の声かけをするッス。
環境エンリッチメントってのも言ってたニャ。
そうッス!快適なクッションとかパパの匂いがついたタオルとか、安心できる環境を作るッス。でも何より重要なのは、痛みがコントロールされることで、行動問題が大幅に改善することが多いってことッス。
なるほどニャ〜。シニアの行動変化は、まず体の問題を疑うのが大事なのニャ。
その通りッス!行動分析は大切ッスけど、医学的な視点を忘れちゃいけないッス。特にシニアの場合は、行動的介入の前に痛み管理の見直しが必要ッスね。